尉と姥伝説
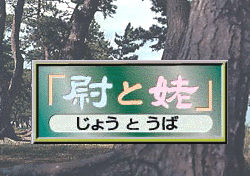

尉(じょう)と姥(うば)のいわれ
その昔、高砂神社の境内に、一本の根から雌雄の幹が左右に分かれた松が生え、「尉と姥」に姿を変えたイザナギ・イザナミの2神が現れ夫婦の在り方を説きました。 以後、この木を「相生の霊松」と呼び、この2神を縁結びと夫婦和合の象徴として信仰するようになりました。
婚儀の際にはおなじみだとおもいますが「尉と姥」は高砂市が発祥の地です。

高砂神社に保存されている三代目相生の松

五代目現在の相生の松

尉姥祭

ちょっと物知り 謡曲「高砂」の話

その昔、九州の阿蘇に友成という神主がおりました。
友成は都へ行く途中、有名な高砂の松を見ようと高砂の浦へ立ち寄りました。

友成がその松をさがしていると、おじいさんとおばあさんが、くまでとほうきを持って松の下をそうじしていました。
友成は、そのおじいさんとおばあさんに

「高砂の松と住の江の松は、遠く離れているのに、どうして相生の松というのですか?」とたずねました。

すると、「相生の松というのは夫婦のようなもので、お互いを思う気持ちがあれば、遠く離れていても心が通じ合うことからそう呼ばれているんですよ。」とおじいさんが、

おばあさんも「松は四季を問わず、一千年も緑色をたたえているということで、たいへんおめでたいとされています。」と話してくれました。
「それは、それは。ありがたいお話を聞かせていただきました。ところで、あなた方はどちらの方ですか?」とたずねると、
「わたしたちは、松の精。住の江で待っていますよ。」
というなり、姿を消しました。

その後、友成は
「高砂やーこの浦舟に帆をあげてー」
とうたいながら住吉へ向かい、そのうたがおめでたいとされ、婚礼の席でうたわれるようになりました。









 PCサイトを表示
PCサイトを表示





更新日:2025年01月27日